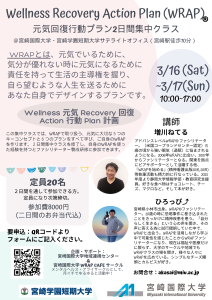開催日:2024/3/9(土) ~ 2024/3/10(日)
場所:青島青少年自然の家
開催日:2024/3/16(土) ~ 2024/3/17(日)
時間:各日 10:00~17:00
場所:宮崎国際大学・宮崎短期大学サテライトオフィス

Watch video
国際教養学部
比較文化学科
SCHOOL OF INTERNATIONAL LIBERAL ARTS
特設サイト

教育学部
児童教育学科
SCHOOL OF EDUCATION
特設サイト


開催日:2024/3/9(土) ~ 2024/3/10(日)
場所:青島青少年自然の家
開催日:2024/3/16(土) ~ 2024/3/17(日)
時間:各日 10:00~17:00
場所:宮崎国際大学・宮崎短期大学サテライトオフィス
ページTOP